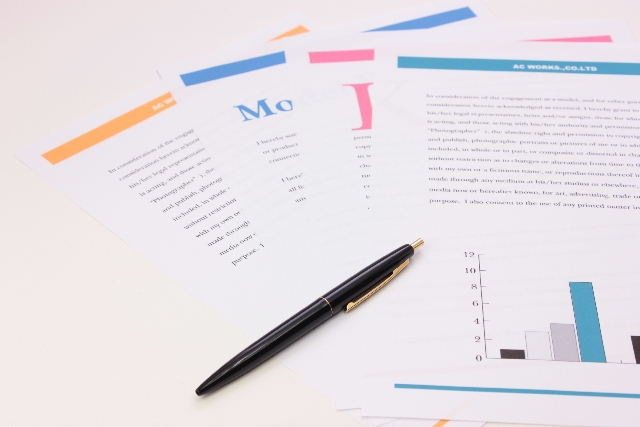


失業保険中にバイトしたいのです。
と言うのが今勤めている会社で正社員からバイトに変えたいのですが、申告をすれば同じ会社でバイトをしてもいいのでしょうか?
バイトといっても次の仕事が決まるまでです。
と言うのが今勤めている会社で正社員からバイトに変えたいのですが、申告をすれば同じ会社でバイトをしてもいいのでしょうか?
バイトといっても次の仕事が決まるまでです。
雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、原則として自由にアルバイトすることができます。
ただし、雇用保険をもらうには失業状態にあって、積極的に求職活動を行っていることが大前提です。そのため、給付制限期間中にも再就職のために積極的な求職活動を行うことが要求されています。具体的には、給付制限の開始から給付制限が終了したあと最初の失業認定日までの間(おおむね4カ月)に最低でも3回以上の求職活動を行ったことを申告しなければならないことになっています。
この大前提があるために、ずっとアルバイトを続けていて求職活動を行わなかった場合には、失業者として認定されず、給付制限終了後の、本来なら失業手当がもらえるはずの日についても支給されなくなってしまいます。
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています
ただし、雇用保険をもらうには失業状態にあって、積極的に求職活動を行っていることが大前提です。そのため、給付制限期間中にも再就職のために積極的な求職活動を行うことが要求されています。具体的には、給付制限の開始から給付制限が終了したあと最初の失業認定日までの間(おおむね4カ月)に最低でも3回以上の求職活動を行ったことを申告しなければならないことになっています。
この大前提があるために、ずっとアルバイトを続けていて求職活動を行わなかった場合には、失業者として認定されず、給付制限終了後の、本来なら失業手当がもらえるはずの日についても支給されなくなってしまいます。
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています
失業保険について質問です。
今月10月末日で、1年7ヵ月正社員として勤めた会社を退職します。
理由はパワハラによるストレスで、医師から心身症との診断書(11月末迄自宅療養の必要ありと記載されていたが、
結局のところ原因が上司のパワハラなので、復帰は困難と判断しました)をもらい、退職届とともに提出しました。
ですので、離職票が出来しだいハローワークに行って失業保険の手続きをしようと思っているのですが、
ちょうど11月中旬から12月末の短期の派遣のお仕事があり、やってみようか迷っています。
もし短期派遣としてでも、仕事をした場合は失業保険はもらえないのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
今月10月末日で、1年7ヵ月正社員として勤めた会社を退職します。
理由はパワハラによるストレスで、医師から心身症との診断書(11月末迄自宅療養の必要ありと記載されていたが、
結局のところ原因が上司のパワハラなので、復帰は困難と判断しました)をもらい、退職届とともに提出しました。
ですので、離職票が出来しだいハローワークに行って失業保険の手続きをしようと思っているのですが、
ちょうど11月中旬から12月末の短期の派遣のお仕事があり、やってみようか迷っています。
もし短期派遣としてでも、仕事をした場合は失業保険はもらえないのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
仕事をなされるのであれば当然失業状態とはなりませんのでどういう雇用形態であろうと
受給資格を満たすとは言えません。
もし短期派遣があるのであれば、雇用保険加入ができるか確認してください。
会社が2社ある場合でも雇用保険加入期間は継続とみなされますので、
短期派遣終了後でも失業保険は受給可能です。
受給資格を満たすとは言えません。
もし短期派遣があるのであれば、雇用保険加入ができるか確認してください。
会社が2社ある場合でも雇用保険加入期間は継続とみなされますので、
短期派遣終了後でも失業保険は受給可能です。
友人の旦那の会社から就業証明書を書いてもらい、保育所に提出し、失業保険をもらったあとに就職できますか?
一歳の息子を持つ専業主婦です。そろそろパートの仕事をしようかと思い、今月8月1日から、子供を保育所に求職中という申請を出して預け始めました。
しかし、先月末に出産で延長していた、失業保険の受給手続きを忘れていたのを気づいて急いで受給手続きに行きました。保育所に入所と同時に今月から失業保険の受給が始まるのですが、保育所は入れてから、三ヶ月以内に就職しないと、退園をさせられるので10月の終わりまでに就職しないといけません。普通に考えて、この失業保険がもらえる三ヶ月の途中で就職を決めて、給付残日数が三分の一以上残っていれば、再就職手当てをもらえる、というようになりますが、一番理想的なのが、最後の三回目の認定日の近くで就職が内定し、10月の終わりから働きだす、そうすれば、失業保険もすべてもらえるし、三ヶ月以内に就職が出くことができてたということで万々歳なのですが、そんな簡単にいくことはないと思うし、もし就職できなかったら退園という恐れもあるので出来ませんが、友人が「私の旦那の自営業の会社で就業証明書を書いてもらって、とりあえずそれを、提出しておいて、失業保険すべてもらってから仕事を決めて、また変更の証明書をだしたら?」といわれ、よくないことはわかっていますが、そういうことは失業保険の受給手続きをしたハローワークにばれたりしないのでしょうか?
他の友人も保育園に預ける際、実家が自営業なので、そこで書いてもらい、仕事を探しています。
一歳の息子を持つ専業主婦です。そろそろパートの仕事をしようかと思い、今月8月1日から、子供を保育所に求職中という申請を出して預け始めました。
しかし、先月末に出産で延長していた、失業保険の受給手続きを忘れていたのを気づいて急いで受給手続きに行きました。保育所に入所と同時に今月から失業保険の受給が始まるのですが、保育所は入れてから、三ヶ月以内に就職しないと、退園をさせられるので10月の終わりまでに就職しないといけません。普通に考えて、この失業保険がもらえる三ヶ月の途中で就職を決めて、給付残日数が三分の一以上残っていれば、再就職手当てをもらえる、というようになりますが、一番理想的なのが、最後の三回目の認定日の近くで就職が内定し、10月の終わりから働きだす、そうすれば、失業保険もすべてもらえるし、三ヶ月以内に就職が出くことができてたということで万々歳なのですが、そんな簡単にいくことはないと思うし、もし就職できなかったら退園という恐れもあるので出来ませんが、友人が「私の旦那の自営業の会社で就業証明書を書いてもらって、とりあえずそれを、提出しておいて、失業保険すべてもらってから仕事を決めて、また変更の証明書をだしたら?」といわれ、よくないことはわかっていますが、そういうことは失業保険の受給手続きをしたハローワークにばれたりしないのでしょうか?
他の友人も保育園に預ける際、実家が自営業なので、そこで書いてもらい、仕事を探しています。
経験があるのですがバレます。
保育園を利用する人の中には
不正を許せない人が多く・・・。
また、就業証明の中には賃金を書く欄もあるし。
止めた方が良いでしょうね。
保育園を利用する人の中には
不正を許せない人が多く・・・。
また、就業証明の中には賃金を書く欄もあるし。
止めた方が良いでしょうね。
扶養と年末調整について
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
1月末まで会社を退職し→1月末で会社を退職し
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
2度目の傷病給付金の受給について
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。
そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。
そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
下記の条件を全て満たせば、同じ病名又は関連する病名でも傷病手当金は支給されます。
1.私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
3.健康保険の被保険者であること。
受給出来る期間は、1度目の傷病手当金の支給開始日後暦日で1年6か月以内です。
また、1度目の病気と異なる私傷病を発病した場合は、次の要件を満たす場合、傷病手当金が支給開始日後最長1年6か月支給されます。
1.私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
1.私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
3.健康保険の被保険者であること。
受給出来る期間は、1度目の傷病手当金の支給開始日後暦日で1年6か月以内です。
また、1度目の病気と異なる私傷病を発病した場合は、次の要件を満たす場合、傷病手当金が支給開始日後最長1年6か月支給されます。
1.私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
関連する情報